お墓の歴史(家制度)と現代の供養形態について解説!
- 2024年7月8日
- 読了時間: 7分
日本の歴史で一族のお墓が生まれたのは江戸時代。さらに明治時代に家制度が規定され、日本では、家とお墓の関係が強くなった歴史を持っています。しかし、現代はこの歴史をぬりかえるかのように、日本人の生活環境に変化がおとずれ、無縁墓が増えたり、墓地を持たない家族や墓じまいをしたりする人も増えているのです。
どの国も歴史を振り返れば、ずっと一様ではありません。歴史を作るのはそこで生活する人々ですから、人の死後に関しても人々の生活が変われば、必然的に変化がおとずれます。そのため、無縁墓や墓じまいの風潮、そして、新たに生まれた供養スタイルである手元供養や、自然に回帰する葬送方法である自然葬などが歴史に加わるのも否めないでしょう。
日本のお墓の歴史
日本の歴史を紐解くと、お墓は家制度と関係があり、ある意味、日本の文化と言えるかもしれません。家制度もお墓も古くから存在し、日本人と深く結びついています。
お墓の歴史は太古のものではなく、江戸時代の中頃からと言われています。ただ、この時はお墓を建てることは富裕層だけのものであり、一般庶民はお墓をまだ持てなかったそうです。また、お墓の歴史に欠かせない檀家制度もこの時代から。そして、明治時代に制定された家制度と融合され、現代まで続く「家」の歴史となっています。
寺院に墓地を持つ家のことを檀家と呼び、その寺院を菩提寺と呼びます。檀家制度では、家が菩提寺にお布施を払い、葬儀やその後の供養をしてもらいます。檀家制度の歴史も江戸時代から始まりました。
家制度とは、日本の家族制度のこと。明治時代に制定された民法の中の規定のひとつが家制度です。家制度は、家族関係の中でさらに狭い範囲で戸主と家族を1つの家に属させ、戸主に家の権限を統率させるものです。この家制度が現代の家の形となっています。
お墓は、家制度と檀家制度により一族でお墓を持つようになった歴史から、今もなお現代に引き継がれています。
ところで、家制度によるお墓には、先祖代々のお骨が納められていますが、お墓に遺骨を納めるには、火葬が必要です。しかし、日本の歴史をみても、以前は火葬よりも土葬が主流でした。世界でも火葬より土葬の国がいまだに多いのは、火葬には多くの燃料が必要だからです。
日本が火葬大国になった歴史には、明治時代に都市部の人口が増加したことから。この時代から火葬が増え始めましたが、地方では土葬でした。しかし、戦後の人口増加と火葬技術の発展により、火葬が一般的になり、今に至ります。
こうしたことより、家、お墓、火葬といった人の生活における歴史は、その時代に適した形で残されていくのがうかがえます。
現代のお墓事情
さて、明治より一変した家制度とお墓の歴史ですが、昨今ではさらに変化を遂げつつあります。
今すぐに家制度やお墓の存在が消えていくわけではありませんが、核家族化が一般的である現代は、先祖代々のお墓から離れた土地で新しい生活を始めたり、海外に移住したりする人も増えています。
そのため、今までの供養スタイルであった墓地を持ち、お墓参りをするといった供養への時間や金銭的な問題を考えると、手元で供養できる手元供養の需要が高まっているのが実状です。
また、少子高齢化により、今までは親族の誰かがお墓を守り続けることができましたが、お墓の継承者不在問題が浮上し、お墓の維持・管理が難しくなっていることから、無縁墓が増えています。そのため、無縁墓を防ぐために墓じまいをし、死後は永代供養を希望する人も多数出てきているのです。
たとえ、新しく墓地を購入するにしても、受け継ぐものがいないことでの無縁墓になる可能性や、都心部での墓地購入が高額であること、葬儀などにお金がかかることなどを考えると、子どもの少ない家庭や子どもがいない家庭では金銭面の大きな負担となり、欲しくても墓地を持てないこともあります。今までは無縁墓や墓じまいなどはあまりなかったようですが、現在は珍しくない時代となり、明治時代から受け継がれてきた家制度、そしてお墓の存在が薄れているのは事実です。
従来のお墓の在り方が、現代人のライフスタイルに合わなくなってきたことで、お墓に対する価値観も変化し、無縁墓や墓じまいといった言葉も飛び交うようになった今、手元供養の需要が高まっていることは必然なのかもしれません。
伝統に縛られない供養のカタチ
手元供養の需要の高まりと同時に、手元供養をするためのさまざまなアイテムが流通しています。
手元供養とは、火葬後の遺骨や遺灰の全部または一部を家に置いたり、指輪やネックレスなどのアクセサリーとして身につけたりして、故人の冥福を祈る方法です。墓地を所有していない、お墓参りに行かないとしても、手元で先祖を供養できるため、手元供養と呼ばれています。
手元供養の種類は、火葬後の遺骨の一部をミニ骨壷に入れて部屋に安置することだけでなく、遺骨をパウダー状にした遺灰を指輪などの一部に納めて身につける遺灰アクセサリーや、遺灰を合成ダイヤモンドに生まれ変わらせる遺灰ダイヤモンドなどがあります。
特に、故人の遺灰から抽出した炭素で作る遺灰ダイヤモンドは、炭素を純度100%近くまで精製し、天然ダイヤモンド同様の環境を再現した装置で精製されるため、天然そのものの輝きを放ちます。そこに故人の輝きがプラスされることで、その美しさは格段なものとなるのです。まるで、故人が傍で生きているかのように輝き続けるため、愛する家族を失った悲しみも和らげると評されています。
遺灰ダイヤモンドは、ダイヤモンドとして安置することもできますが、指輪などにジュエリー加工もできるため、メモリアル指輪として身につけることも可能です。いつも故人と一緒にいられることで日本のみならず、世界中で遺灰ダイヤモンドの人気は高まっています。
どのような形態でも手元供養は、墓地の購入価格やお墓の維持継承にかかる金額より、はるかに安く価格が抑えられる点がメリット。少子高齢化の時代にはふさわしいスタイルでしょう。
また、地方にあるお墓を墓じまいたり、新しく墓地を購入できなかったりといった理由から自然葬にも注目が集まっています。
自然葬とは、火葬した遺骨や遺灰を海や山などの自然に回帰させる、墓石などの人工物を使用しない葬法です。自然葬にもさまざまな形態があり、中でも遺灰を海や湖にまく海洋散骨、樹木の下に遺灰や遺骨を埋葬する樹木葬などが人気です。
自然葬は、墓じまいしたときに残される先祖の遺骨の改装にも最適であり、価格も墓地購入やお墓継承よりは抑えられる点で好まれています。ただし、故人の思い出が手元に何も残らないというデメリットもあるため、遺灰ダイヤモンドなどの手元供養と同時に行う人が多数います。
まとめ
日本の歴史におけるひとつの大変革期は明治時代。ここで家制度が始まり、現在の家のスタイルが確立されました。また、お墓の歴史は江戸中期から始まり、江戸時代に確立された檀家制度は家制度と組み合わさり、一族に墓地とお墓が誕生しました。
そして、今でこそ日本は火葬大国ですが、土葬の歴史を長く持ちます。しかし、人口増加により、国土の狭い日本では土葬のための墓地を確保するのは難しくなり、火葬技術の進歩も加わり、明治時代から火葬が増えていきました。
このような日本人の生活における歴史は、今まさに変貌しつつあります。昔のように子どもをたくさん作らなくなった家庭、墓地のある地元を離れて人生を送る人々、時代とともに変化するライフスタイルが、お墓のへの価値観を変えています。
家族をもたないために無縁墓になるケースも多く、無縁墓になることを阻止するために墓地を持つことをやめたり、墓じまいしたりするのも現代ならでは。また、お墓の継承者不在による墓じまいも多数行われています。特に墓じまいは、お墓の継承にかかる金銭的な理由もあるようです。
こうした無縁墓や墓じまいに取って代わる新しい供養スタイルが、自然葬や手元供養。火葬した遺骨を遺灰にし、海に撒いたり、樹木の下に埋めたりする自然葬と、遺灰を指輪などのアクセサリーに納めて身につけたり、故人の遺灰から抽出した炭素で遺灰ダイヤモンドを作製して供養したりする手元供養の需要が高まってきているのです。手元供養は、故人を身近に感じることができる点、墓地購入価格やお墓の継承値段に比べて、安い価格で実施できる点でも人気があります。
人々の生活様式に合わせて変わる供養スタイルですが、ここで着目したいことは、どこにいても故人を想い、冥福を祈る、人としての気持ち。時代や生活は変わっても、人の気持ちは変わらないために、さまざまな供養スタイルが増えてきている時代だということでしょう。
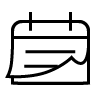
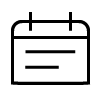
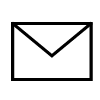
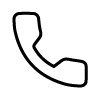







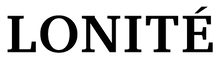



コメント